
吉田恵子さん
吉田恵子さん
【プロフィール】1979年NHKカルチャースクールでパッチワークキルトを学び始める。1985年「AIQAキルト・フェスティバル」(テキサス州・ヒューストン)出品。「キルト‘85」(スイス)招待出品。「キルト・イン・ジャパン’85」入選。1989年「女流クラフト作家展」出品。「AQSキルト・フェスティバル」(ケンタッキー州・パデューカ)出品。「ザ・グレート。アメリカン・キルト・フェスティバル2日本の宝石達」(ニューヨーク)特別出品。1990年「キルト展」(ニューイングランド・キルト美術館)出品。アトリエ「ウェーブK」主宰。

「時のうつろい」1998年制作 156×192cm
強い夏の日差しの中で咲くのうせんかずらに惹かれて、いつかはキルトにと思って作った作品。左側は咲いている様子を、右側は冬枯れの枝を表したかったのだという。庭に植えて観察してみると、冬になっても緑の葉は延々と元気で力強く冬越えする姿に圧倒された。そこで右側のデザインは夏の面影をグレーで、周りのフィルムは時の流れを写真の形で表現している。
端布を素敵に見せたくて始めたパッチワーク
吉田さんは、幼稚園の先生を3年間した後、に24歳で結婚。それから一般募集で見つけたテレビ局のアルバイトの教育係、お花の先生、そしてキルトの先生と、見事に自分の適性に即した人生を歩んでいる。
「おしゃべりは、ちっとも苦にならないんですよ。キルトの授業も、その日の話の枕が長すぎて『先生、そろそろキルトを始めましょうよ』と生徒に言われたりして(笑)。でも、キルトは楽しくやるのが私のモットー。笑いの中で、きちっとしたものも学ぶから楽しいんですよね」
キルトとの出会いは、30歳を過ぎてからだった。その前に幼稚園の先生をしながら、洋裁学校に通った。洋服作りで出る端布をはいでみたが、どうも素敵に見えない。1枚1枚は素敵な布なのになぜだろう、というはがゆさが残った。
30を過ぎ、そろそろ子どもが欲しいと考えて忙しいテレビ局の仕事を辞めて、家庭に入った。その頃「あなたの持っている残り布が素敵に変身します」というキャッチフレーズで目に止まったのが、NHKカルチャースクールのパッチワーク教室だった。
行ってみるとみんなパッチワークについて詳しいし、器用な人ばかりにみえる。これはかなわないと、1年ばかりはいつやめようかと思っていたそうだ。でも、ひとつずつ課題をこなすうちに辛抱強さも培われ、知らぬうちにキルトにはまっていた。
お茶とお花がキルト制作のバックボーンに
「やる前は考えるけど、いったんやり始めたら長く続く」という性分の吉田さん。お茶とお花も長らく続けていたが、そこで育った美的感覚はキルトの世界でも貴重なバックボーンとなった。
お茶は、母の薦めで小学校6年生から習い始め、十年間稽古に通った。とりたてて一生懸命覚えようとしたわけではないが、茶道のお手前というのは、無駄なく美しく合理的にできている。そんな所作が、子どもの頃から身についたからか、お茶碗はほとんど割らないという。
「こども心にも、お茶の稽古の時間は、時が止まるように感じましたね。鉄瓶がちんちんなる音や、袱紗を払う密やかな音しか聞こえない、とても静かな時間が子どもにも心地よかったのでしょうね」
そして吉田さんの大好きな、お花。19歳から始めた花月流を28歳で教え始め、45歳でキルト1本に絞るまで、平面分割、色彩学などの総合的なセンスの多くを、お花の世界で学んだ。
「西洋の美はシンメトリーですが、日本はどこかバランスを崩した美ですよね。そして、西洋が足し算の美とすれば、日本は無駄なものをどんどん削っていく引き算の美です。私のキルトも、一見洋風な作品ですけど、アメリカに持っていくとすごくエキゾチックと言われるの。やっぱり、日本人の中に脈々と流れてきた美意識が、自分の中にも存在しているのだと思いますね」
イメージをつかみ、タイトルを決めて突っ走る
吉田さんが花の中でも一番好きなのが、バラとチューリップ。取材の日も大輪のカサブランカに組み合わせて、ことに好きなオレンジがかったベージュのバラが生けてあった。
バラの純粋さや可憐さは百態変化で、見る人を魅了せずにはおかないものがあるが、チューリップは花材として惹かれたことは一度もなかった。それが俄然興味深いものになったのは、花弁がギザギザになった珍品種は、もとはウイルスの侵されたものだったとか、黒いチューリップに球根は番人がいたというくらい貴重だったという歴史やいわくを知ってからだ。それからドレスデンのアンティークプレートなどを気を付けて見ると、実にさまざまな表情のチューリップがあり、ますます興味が湧いてきた。

アトリエのあちこちに置かれた、お宝箱や家具の中や上にはイギリスやアメリカなど外国旅行で買い求めたという、アンティークなレースやリボン、ボタン、陶器などがいっぱい詰め込まれている。
─本文より一部抜粋─ キルトジャパン2002年3月号より
ライタープロフィール
・キルトジャパン編集部
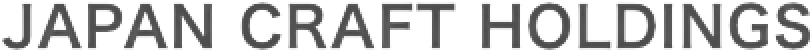



 カート
カート



























